働きやすさがつなぐ子どもの安心 ― 社会福祉法人風の森の実践
2025-08-28
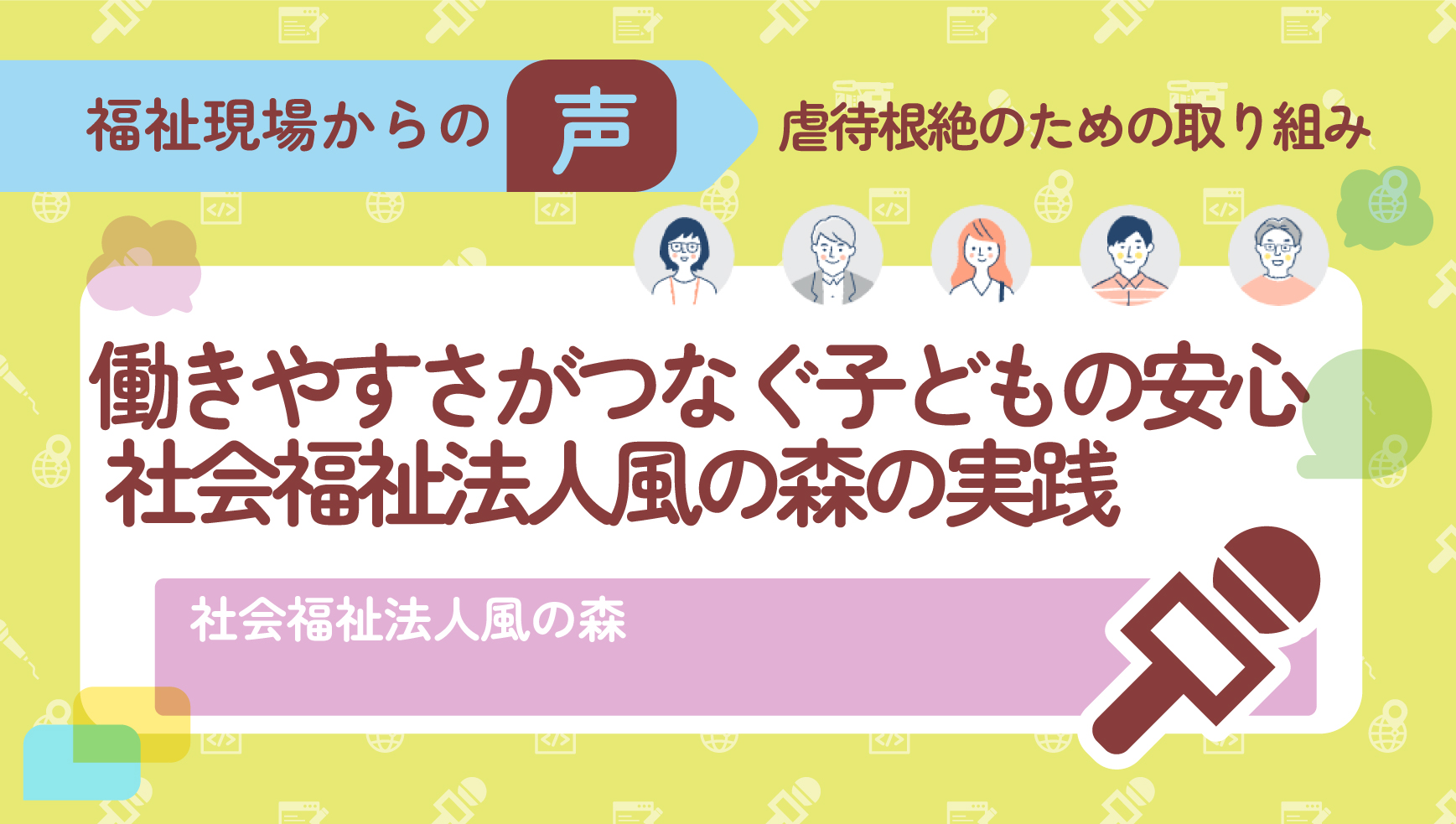
社会福祉法人風の森 法人統括 野上美希
職員が安心して働ける環境が子どもを守る
東京都杉並区。住宅街の一角にある社会福祉法人風の森が運営する認可保育園には、朝から元気な声が響いています。園庭では子どもたちが走り回り、先生たちの笑顔とが絶えません。その様子は、ただ子どもが安心して過ごせる場であるだけでなく、職員自身が安心して働けていることを映し出しています。
「権利擁護や虐待防止は、特別なプログラムを用意することよりも、職員がゆとりを持って働ける環境を整えることから始まる」。野上美希統括はそう語ります。権利擁護を制度の一部にとどめるのではなく、日常の文化として根づかせること。それが風の森の大きな特徴です。
風の森の母体には、75年以上の歴史を持つ「久我山幼稚園」をはじめとする野上学園の教育事業があります。その経験を基盤に、平成25年に法人を設立。翌年に最初の保育園を開園し、現在は認可保育園6園、病児保育室1園、児童発達支援事業所1園を運営する規模へと成長しました。
特徴的なのは、事業展開を杉並区内に限定していることです。背景には、働き方の柔軟さを守るという明確な狙いがあります。女性が多い職場では、妊娠や出産、育児といったライフイベントに合わせて働き方を変える必要が出てきます。複数の園を同じ区内に展開することで、職員は生活環境に応じて異動が可能になり、働き続けやすくなるのです。
また、自治体ごとの制度の違いによる混乱を避け、同一地域でノウハウを共有できることも大きな利点です。制度の差を超える調整負担を抱えずにすむため、法人全体として安定した経営と現場支援が実現しています。

手厚い職員配置と積極的なICT活用が生む「寄り添う保育」
採用においても風の森は安定した成果を上げています。現在の中途採用倍率は18倍。全国から「ここで働きたい」と志望者が集まります。その理由のひとつが、国の基準を大きく超える2倍の職員配置です。
現場には子どもの直接的な保育以外にも、掃除や書類作成、シフト調整といった業務が多く存在します。基準通りでは対応しきれない部分を、手厚い配置によって補っているのです。
財源は、国や自治体の補助金や追加配置制度に加え、一時預かりや職業体験といった付帯事業で確保しています。そのため採用コストはほとんどかからず、自然に応募が集まる状況が生まれています。
働きやすさだけでなく「子どもに寄り添った保育ができること」を志望動機にする応募者が多いのも特徴です。採用ではその姿勢を重視し、結果として保育者同士が切磋琢磨する文化が育まれています。
研修もすべて勤務時間内で実施し、年度初めには園長や主任と話し合って一人ひとりの学習計画を立てます。園長を目指す人、マネジメントを志す人、現場で専門性を深めたい人。それぞれのキャリアビジョンに応じた支援が行われています。
風の森ではICTの活用にも積極的です。各園にはクラス数以上の端末を備えるのは当然。音声入力も導入可能ですが、保育室で声を出すと子どもが反応してしまうため、タイピングを基本としています。
ICT導入の目的は単なる効率化ではありません。「今ある業務をデジタル化する」のではなく「業務そのものをどう変えるか」という視点が重視されています。たとえば、従来は月1回だった保護者へのお便りを毎日配信に変えたり、文字だけでなく写真やイラストを加える工夫をしたりと、ICTを活用して伝え方自体を進化させています。
効率化によって生まれた余裕は、子どもについて話し合う時間や職員同士のコミュニケーションに活かされています。つまりICTは「子ども中心の保育」を支える基盤となっているのです。

日常に根づく権利擁護の仕組み
風の森では、子どもの権利を守る取り組みを特別な活動としてではなく、日常の延長に位置づけています。その中心となるのが、業界団体が作成した「権利に関するチェックシート」を使った自己点検です。年に一度、全職員が自らの言動を振り返り、同僚と確認し合います。
「お化けが出るよ」という何気ない声かけが実は虐待にあたると知ったとき、全職員が表現を改めました。また「ちょっと待ってね」という言葉も議論になり、最終的に「言葉そのものより職員が余裕を持っているかどうか」が重要であると確認しました。
権利擁護を支えるのは、心理的安全性を重視する文化です。法人本部はわずか3名という小さな体制ですが、その分、園長や職員の声が埋もれることなく反映されます。気になる言動を率直に伝え合い、園長には「責める」のではなく「一緒に改善する」姿勢で相談できる。そうした風土が、重大な問題に発展する前に芽を摘むことを可能にしています。
虐待が疑われる事態が起きた場合は、まず園長へ報告し、必要に応じて関係機関と連携する流れがマニュアル化されています。しかし何よりも大切なのは、普段から相談できる関係性を築いておくこと。安心して働ける環境が、子どもの権利を守る最前線になっています。
こうした取り組み全体を通して見えてくるのは、風の森の実践が制度やマニュアルに頼るのではなく、職員が安心して働ける環境を整えることで子どもの権利を守るという姿勢に貫かれている点です。手厚い職員配置、ICTの柔軟な活用、心理的安全性を重視する文化。これらが相互に作用し合い、職員がゆとりを持って子どもに寄り添える土壌を築いています。「権利擁護は特別な活動ではなく、日常そのもの」。野上統括の言葉の通り、働きやすさと働きがいが結びついたとき、子どもたちの安心と健やかな成長が支えられていきます。
