児童の権利を守るための具体的な取り組み
2025-03-31
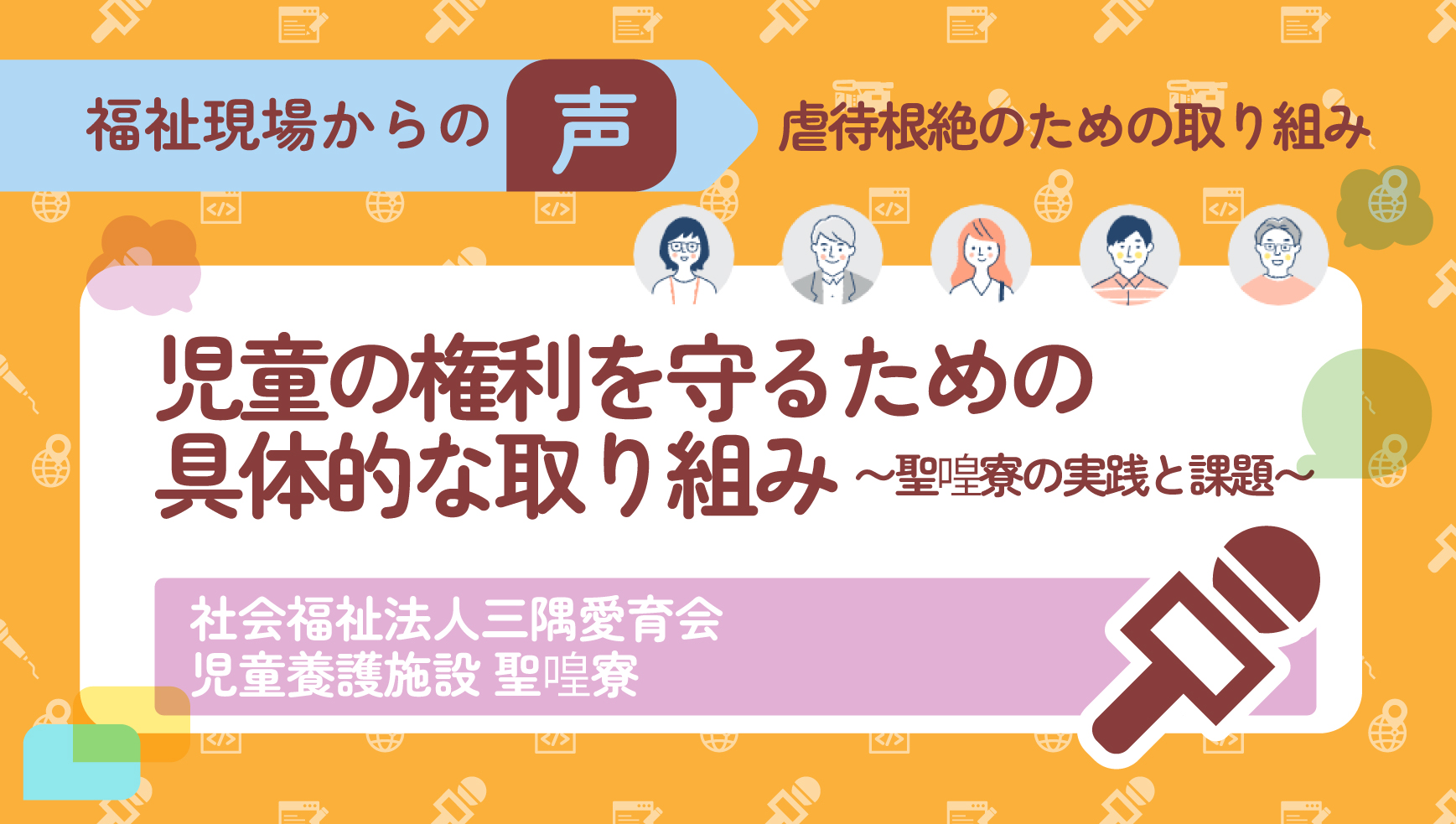
児童養護施設 聖喤寮 主任児童指導員 佐々本 良子
施設の特色と職員の葛藤 〜子どもたちの生活を支える難しさ〜
聖喤寮は、自然豊かな環境の中で、子どもたちが安全に安心して生活できる施設です。定員42名のうち、現在22名の児童が暮らしており、職員数は28名(パート含む)です。家庭的な雰囲気を大切にするため、小規模ユニット制を採用し、6人ごと(定員)のユニットで生活しています。
施設では、子どもたちの生活リズムを整え、社会性を育むための支援を行っていますが、一人ひとりの過去の経験や心の状態が異なるため、職員の対応には柔軟さが求められます。
例えば、過去に家庭環境が不安定だった子どもは、生活習慣を整えることに戸惑うケースが多くあります。食事の時間に慣れず拒否する子どもや、夜になると不安が高まり眠れなくなる子どももいます。職員は「少しずつでいいよ」と声をかけながら、無理のない範囲で食事の習慣を整えたり、安心して眠れる環境を作ったりと、個々のペースに合わせた支援を行っています。
また、高校生にとって、施設の門限は自由と規律の象徴となることが多くあります。ある男子は、行事の打ち上げに参加したいと強く希望しましたが、施設には門限があるため、「普通の家庭の子はいいのに、どうして自分だけがダメなのか」と反発しました。職員は安全管理の重要性を説明しつつ、どこまで譲歩できるかを模索し、何度も話し合いを重ねているところですが、職員にとっては自由と規律のバランスを取る難しさを痛感する事例でした。
一方で、安全確保のために職員が身体的に制止せざるを得ない場面もあります。例えば、施設を飛び出そうとする子どもにはまず説得を試みますが、それでも制御が難しい場合には、やむを得ず介入を行い、落ち着くまで見守ることもあります。こうした判断は職員にとっても葛藤を伴うものであり、自由を尊重しながらも、施設の規律と安全を守る難しさに常に直面しています。

子どもの声を受け止める 〜権利擁護のための日常活動〜
聖喤寮では、子どもたちの権利を守るため、以下のような具体的な取り組みを行っています。
・子ども自治会の運営:施設生活のルールや要望について話し合い、職員とともに改善策を考えます。/・意見箱の設置とフィードバック:意見箱に寄せられた声は、県庁青少年家庭課や児童相談所と共有し、適切な対応を取るよう努めています。/・個別聞き取りの実施:担当職員が毎月25日前後に児童一人ひとりの意見や悩みを聞き、支援方針を検討します。施設長との誕生日面接を行い、大きくなり成長したところを伝え、子どもの意見や悩みを聞きます。また、「子どもアンケート」を行い、子ども達が安心して安全に暮らせる様に子ども達の意見を聞きます。
――こうした活動を進める背景には、子どもたちが主体的に自分の意見を表現し、より良い生活環境を築ける場を提供したいという思いがあります。聖喤寮では、子どもたちが単に施設のルールに従うだけでなく、自分たちの暮らしに関わる決定に積極的に参加できることを大切にしています。
例えば、自治会の導入は、子どもたちが自分たちの環境をより快適にするための意見を出し合い、実際に改善につなげる機会を作るために始まりました。子どもたちが「こんな活動をしてみたい」、「もっと過ごしやすい空間にしたい」といった前向きな意見を交わし、それを実現するプロセスを体験することで、主体性を育んでいます。
また、子どもたちが安心して自分の気持ちを話せる環境を整えることも大きな目的の一つです。しかし、こうした取り組みがすぐに子どもたちの気持ちを前向きにさせたわけではありません。
初めのうちは、「どうせ意見を言っても何も変わらない」と考え、自治会で発言しない子どもや、職員との話し合いを避ける子どももいました。過去の経験から大人への不信感を抱えていたり、自分の気持ちを表現することに慣れていなかったりする子どもも多かったのです。
しかし、職員が根気強く耳を傾け、実際に子どもたちの要望を反映させることで、少しずつ「意見を言ってもいいんだ」と感じるようになりました。例えば、ある子どもは「誕生日会をもっと子ども主体でやりたい」と提案し、次年度職員がサポートしながら実現していく方向で動いていることを子ども達に伝えることで、自分の意見が尊重された経験を積むことができ始めています。
このように、信頼関係の構築には時間がかかりますが、継続的な取り組みによって、子どもたちは自分の意見が大切にされる場があることを実感し、自立に向けた準備ができるようになっています。

未来を守るために 〜虐待防止のための体制〜
虐待を防止し、子どもたちが安心して過ごせる環境を作るため、聖喤寮では以下のような体制を整えています。
•暴力防止検討委員会の設置:毎月開催し、児童の問題行動や職員の対応について検討します。例えば、子ども同士のトラブルや、生活ルールに関する問題が発生した際、具体的な対応策を話し合います。最近では、ある児童が感情のコントロールが難しくなった子どもが、他の子どもと衝突することが増えたため、どのように声かけをするべきか、支援方法を検討しました。委員会では、職員が共通の対応をとることで一貫した支援ができるようマニュアルを作成し、実践しています。/•外部専門家による研修:島根県立大学の藤原映久教授を招き、安心・安全な施設文化構築のための児童の権利擁護や虐待防止に関する最新の知識を学んだり研修を受けたりする機会を設けています。研修では、児童間暴力を未然に防いだり、子どもの自己表現を促したりするための具体的な支援技術について学びます。例えば、過去の事例をもとにしたロールプレイを実施し、実際の現場でどのように対応すべきかのシミュレーションもしています。職員はこの研修を通じて、より実践的なスキルを身につけています。/•緊急対応マニュアルの策定:不測の事態に備え、実際の事例を基にした研修を実施しています。例えば、施設内で子どもが感情的に不安定になり問題行動を起こした場合、職員がどのように声をかけ、どの段階で介入すべきかを実際に模擬ケースを設定し、複数の職員が役割を決めて対応をロールプレイしました。これにより、現場での冷静な対応を可能にし、子どもの安全を確保するための体制(緊急対応マニュアル)を整えています。
――児童養護施設の職員は、日々さまざまな葛藤を抱えながら子どもたちと向き合っています。
≪子どもの信頼を得るまでの時間≫虐待を受けてきた子どもたちの中には、大人への不信感を強く抱いている子も多くいます。そうした子どもたちが心を開くまでには時間がかかり、職員は根気よく関わり続ける必要があります。決して焦らず、粘り強く接し続けることが求められます。/≪自由と安全のバランス≫職員は、子どもたちが自由にのびのびと生活できる環境を提供しつつ、安全を確保しなければなりません。しかし、これらのバランスを取ることは非常に難しく、時には子どもの自由を制限せざるをえない場面もあります。反発する子どもを前にして職員にとっても「本当にこの対応でよかったのか」と悩む瞬間が日々あります。子どもの自由を尊重しながらも、安全を守るために介入することの難しさを痛感します。/≪社会の理解とのギャップ≫こうした児童養護施設の職員の現実や努力は、あまり社会的に認知されているわけではないということは残念ですし、誤解もあります。私たちは子どもが安心して安全に生活をし、心身共に健やかに成長できるように養育支援に努めています。
――職員が子どもたちと向き合い続けられるのは、「一人でも多くの子どもが安心できる未来を築けるように」という思いがあるからです。そして、その思いを社会全体が理解し、支えていくことが、より良い児童福祉の実現につながるのではないでしょうか。
