報告制度とデータ分析で虐待の芽を逃さない
2025-02-28
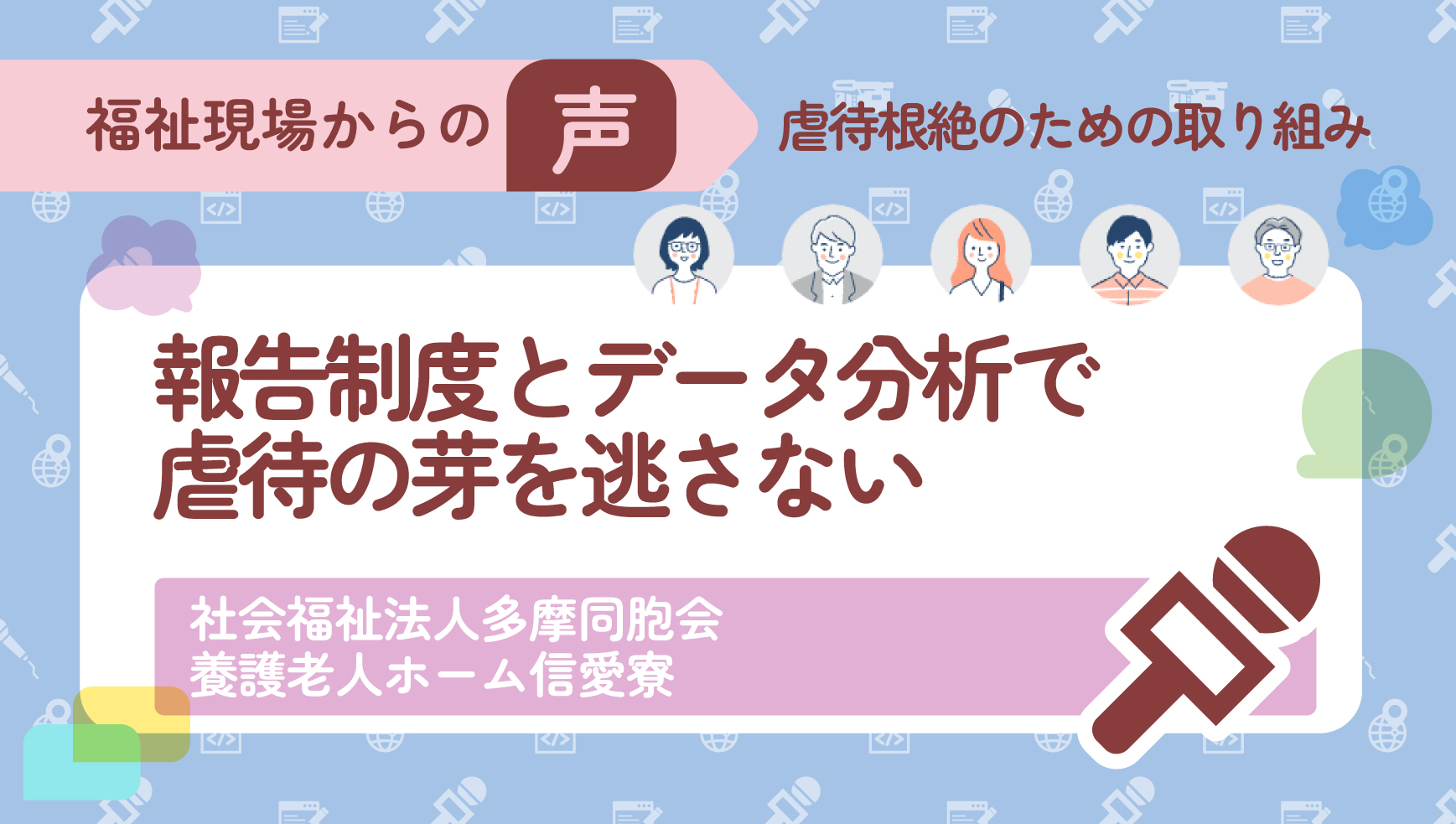
養護老人ホーム信愛寮は、府中市の閑静な住宅街の一角に位置する施設です。全室個室を整備し、利用者の「すこやかに自分らしい暮らし」を支援しています。また、介護が必要になっても、住み慣れた場所で暮らすことができるように、特別養護老人ホーム信愛緑苑を併設しています。今回は、信愛寮の地域での役割と虐待防止のための体制についてお聞きしました。
社会福祉法人多摩同胞会 養護老人ホーム信愛寮 施設長 金井英明
虐待被害から守るシェルターとしての役割
信愛寮は、地域の方々を虐待被害や危機的な状況から守るシェルターとしての役割を大きく担っています。現在、入所者の約7割近くが、なんらかの形で虐待を受けた方々です。また、セルフネグレクトにより生存権が脅かされるケースも急増しています。セルフネグレクトも虐待の一種であり、介護が必要でなくても支援を必要とする方が増えているのが現状です。信愛寮では、そのような方々を受け入れ、安全な生活を支える役割を果たしています。
虐待被害を受けている方が養護老人ホームに入所するまでの過程では、地域包括支援センターが関わることが多いです。「これは虐待ではないか?」と思うケースでも、発見した人がすぐに行政へ虐待通報をするのは、非常にハードルが高いのが現状です。そのため、最初の相談先として重要な役割を果たしているのが地域包括支援センターです。
地域包括支援センターは、相談を受けると行政の担当者と情報を共有し、解決へ向けた対応を進めていきます。また、行政の担当者と地域包括支援センターの社会福祉士が二人一組で虐待防止の研修を受講するなど、虐待を発見した際に迅速に対応できる仕組みと研修体系が整えられています。
最初に虐待の可能性に気づくのは、ケアマネジャーやサービス提供事業者、あるいは地域包括支援センターの職員かもしれません。しかし、発見したからといってすぐに「では、シェルターへ入所しましょう」とはなりません。まずは、実態を正確に把握するための訪問や調査が必要です。
家族との関係性や介入の方法によって、適切な接し方や調査の進め方は変わります。そのため、状況に応じた柔軟な対応が求められます。介入の結果、状況が改善しない場合には、虐待と認定したうえで家族との分離を検討し、必要な支援へとつなげていく流れとなります。

報告の徹底と統計データでリスクを防ぐ
信愛寮では、「ヒヤリハット」という概念を廃止しました。事故には必ず何らかの因子があるため、「ヒヤリハット」と事故を区別せず、すべてを事故報告書として記録し、報告を徹底しています。
法人内では、事故を五段階に分類し、事故報告の流れを厳格に定めています。具体的には、当日の施設管理者には事故発生当日に必ず報告し、管理者は三日以内に施設長へ報告、施設長は七日以内に業務執行役員へと確実に伝達される体制を整えています。すべての報告を文書として残し、月に一度、施設内で情報を集約したうえで、併設特養と合同で開催する権利擁護虐待防止検討会議にて検証を行い、事故の因子を明らかにしています。さらに、毎月具体的な予防策や対策を策定し、実践しています。
例えば、転倒リスクの高い入所者に対しては、家具の配置を変更するのが適切か、センサーマットの導入が有効かなど、ケースごとに具体的な対策を検討します。事故の因子は、一つひとつは小さいものの、見落としやすいため、日常の介護の中で「当たり前」と思われていることを細かく検証し、小さなステップで改善を積み重ねることを重視しています。
また、統計的な分析も行い、発生しやすい時間帯や体制などを把握することで、事故の傾向を可視化しています。個別の検証と併せて統計資料の分析も毎月実施し、施設全体の安全性向上に努めています。
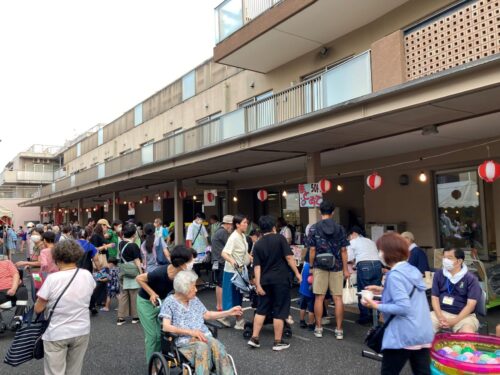
チェックリストの活用で相互に気づき合う
職員の雇用形態はさまざまで、正職員であれば外部の虐待防止研修に参加する機会がありますが、短時間勤務の職員は受講が難しいこともあります。そのため、入職時にすべての職員に対して虐待に関する説明の機会を設け、基本的な理解を深められるようにしています。
福祉の仕事が未経験の職員もいるため、虐待についての知識をさらに理解を深めるには、実際の現場経験を積むことも重要です。そこで、日常業務の中で具体的なケースを共有し、学びを深める機会を設けています。
また、定期的に「虐待の芽チェックリスト」を用いたチェックを実施し、その結果を統計化して次回の会議で職員に配布しています。結果を振り返ることで、新たな気づきが生まれることも少なくありません。
例えば、ある項目について「自分はやっていない」と認識している職員が多い一方で、「他の職員がやっているのを見たことがある」と回答する職員がいるケースがあります。このように、自身では気づいていなくても、他者の視点からは異なる行動が見えることがあります。そのため、信愛寮では「思いのほか、自分では気づけないことが多い」という視点を持ち続けることの重要性を職員に伝え、注意喚起を続けています。